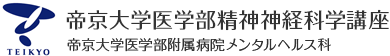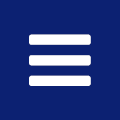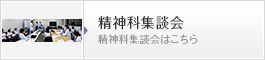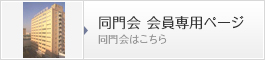精神科学教室 活動報告
第4回認知症 手をあてるフォーラム
2018.07.10
平成30年7月7日、TKP品川カンファランスセンターにて「第4回認知症 手をあてるフォーラム」が開催された。工藤千秋先生という、大田区で開業されている先生が主催されている会で、地域の医療関係者を対象にしたものかと思うが、あえて足を運んだのは特別講演の演者が松下正明先生だったからである。
松下先生は私が医学生だった頃に東大精神科の教授を務めておられ、私の卒業よりも前に退官された。同窓会などで謦咳に接する機会はあったものの、講義を受けるのは学生の時以来20年ぶりである。当時の教授試問では、私は「病棟に入りやすいよう、学生に鍵を持たせてほしい」などと、今自分自身が接している学生たちと何ら変わらない訴えをしていた記憶がある。今回、「皆さんの常識を覆す話をします」という前置きで始まったお話は、アルツハイマー型認知症についての独自の、しかし本質的で明晰なご見解や、ユマニチュードなどの最新の知見、それに高齢者に対する差別・偏見などの社会的問題への警告も含まれていて、興味深いことばかりだった。そればかりか、最近、本格的に認知症診療に取り組み始めた私の疑問・不安などまでもがきれいさっぱり吹き飛ばされてしまったのは、50年にも及ぶ先生の臨床経験から得たヒトの老いと死についての達観、それに世俗の雑事から離れてますます自由闊達に見える知性のなせるところであろうか。自分はこんな立派な先生の教えを受けていたのかなあ・・・と恥じ入るやら、有難いやらで、何か高僧の法話にでも接しているような気分であった。
最後に、先生が最後のスライドで示されたメッセージを以下に転載させて頂く。
「認知症医療にたずさわる専門家には、知を深め、技を磨き、人間理解に努め、それを基礎として、社会に隠然として存在する、高齢者や認知症の人などの弱者に対するステレオタイプ、偏見と差別、虐待、そして排除・抹殺という思想や行為に対する闘いへのリーダーシップを発揮して、敢然と立ち向かっていく社会的使命がある。この社会的使命を果たすことが、即、認知症の人を支えることでもある。」
栃木衛
第14回板橋区認知症を考える会
2018.06.21
平成30年6月20日、板橋区医師会館において第14回板橋区認知症を考える会が開催されました。この会は、板橋区の認知症対策を検討するため、板橋区医師会、東京都老人総合研究所・老人医療センター(現健康長寿医療センター)の有志により平成16年に発足し、その後、自治体主導の認知症対策事業が活発となったため活動が一時休止されていましたが、今回、板橋区内や周辺医療機関との情報共有、医療の均てん化を目的として活動を再開することになたということです。当科からは栃木が委員として初めて参加させて頂きました。当日は、東京都ならびに板橋区における認知症施策について説明があり、また当院も含めた参加医療機関、城北地区医師会から現状報告がなされました。これまでにもお世話になっている医師会の先生方、行政機関の職員の方だけでなく、関連医療機関の先生方ともご挨拶や情報交換をすることができ、今後の当院・当科の認知症診療の展開に向けて大きな足掛かりを得た思いでした。会の目的に沿って、これまで以上に努力していきたいと思います。